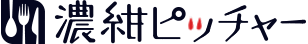自家製味噌
はじめて味噌を仕込んでみました。家庭でも簡単にできました。
自家製のお味噌、オススメです!

みそが自宅で作れるの知っていましたか?

自家製味噌を作りました。写真は、私が作ったお味噌です!
今自宅の味噌汁はこの味噌を使っています。
かつお節などからダシをとり、自分が作った味噌で作る味噌汁は格別です。
作ったキッカケ
味噌が有名な愛知県出身の友達のお家で頂いた味噌。
おいしいなーと思って聞いたら、自家製のこだわり味噌だとのこと!
簡単だから作ってみなよ!というわけで、私も自家製味噌にチャレンジしてみることにしました。
味噌を作る時期は、雑菌が少ないと言われている涼しい時、寒い時がいいと言われていて、12月から2月くらいに仕込む寒仕込みがいいようです。
米糀を買いに
まずは準備。味噌作りに大事な糀(こうじ)を手に入れます。

おしゃれなパッケージですね。
こちらの「生の米糀」です。
直接買えるお店は都内には少ないのですが、今回はその中のひとつ、神田にある天野屋さんに行ってきました。
天野屋さんへ行ってみる
天野屋さんは、創業1846年という老舗です。神田明神の鳥居の隣にあります。

本当に真隣ですね!とてもいい立地。平日でしたが、お客さんもひっきりなしでした!

160年以上続くお店では、生の米糀の他に、あま酒、納豆、塩糀セットなどが売られていました。
隣に併設されている喫茶室もあり、あんみつやわらび餅、あま酒などがいただけます。
ちなみに、買いに行った3月3日のひな祭りの日はちょうど、1年に一度のあま酒を無料でいただける日でした。
この甘酒が本当〜〜に美味しかったので、自宅用にも買いました!ちなみに通信販売もあるそうですよー。

料理の手順
- 大豆を洗い、水に18時間以上つけておく
- 大豆をアクをとりながら4〜5時間煮る
- 大豆をつぶす
- 糀と塩を混ぜる
- 糀と大豆を混ぜあわせる
- 容器につめる
- 重石をして冷暗所に置いておく
特に、大豆を洗うところと、煮込むところが大変そうだ。
大豆をどれくらいつぶすかがポイントかな。
うむー、味噌作りは、一度やってみないと何にもわからないですね。
今回は、出来上がり約2kgを目指して、大豆460g、米糀460g、塩230gを用意しました。2kgは少ないかもしれないですが、まず手始めにという事で。
味噌の材料(2kgくらい)

料理開始
味噌作りスタート
まず、大豆の計量をします。

たっぷりの水でよく洗います。

水が汚れてきました。きれいに見えて、結構汚れが付いているんですね。泡が出てくる。。

水が透明になるまで、しっかりと洗います。

きれいになりました!

しっかり洗ったら、大豆の3〜4倍の水に浸けます。

水を吸って膨張するので、多めの水がよいですね。
ラップをかけて、これから18時間くらい置きます。

途中経過、12時間後です。だいぶ大きくなりましたね。

18時間後の豆です。これで吸水は十分ですね!

濃紺さんの隣で、数粒もらって実験していました。
最初は、こんなシワシワの豆です。

12時間後、水を吸ってふっくらしてきました。

18時間後、水を十分吸ってパンパンです。

大豆を煮込む
水を切ります。

鍋に豆を入れ、ヒタヒタくらいの量の新しい水を入れたら、弱火で4時間〜5時間、コトコト煮ていきます。

圧力鍋を使えば、短時間でできるのですが、大豆の皮が詰まってしまうことがあったり、アクが取れないのが心配なので、鍋で時間をかけることにしました。
しばらくすると、アクが出てきます。

結構なアクの量ですね。

マメにアクを取っていきます。

大豆が頭を出しそうになったら、水を加えます。

繰り返していたら、アクがだんだん減ってきました。

煮汁に色がついてきましたね。

どんどん煮汁の色が濃くなっていきます。

5時間煮た煮汁は、こんなに濃くなりました。
これ、煮過ぎてるような気もしますね。。

なんと、この煮汁は栄養があり、味噌汁などに使うと、味がまろやかになるのだとか!
固さは指でつぶれる程度になれば大丈夫です。
大豆をつぶしていく
豆が煮えたら、準備しておきたいのは、米糀です。

これが米糀ですか。お米が乾燥しているような状態ですね。
塩を計量します。

塩と米糀をよく混ぜます。
ボウルの下からやさしくすくうようにして、糀をつぶさないように。

煮汁を切ります。

この煮汁はとろとろしてますね。
これから大豆をつぶしていきます。
つぶす方法は色々あると思いますが、まずは煮汁を少々加えて、ミキサーにかけてみました。

ウィーンとやってみます。

あ、ペースト状になってしまった。。
これはやり過ぎですね。見た目、レバーペーストです。

ミキサーはやめましょう。ジップロックにいれて、手で潰してみました。

柔らかいので、簡単につぶれます。

手でつかんだりして、さらにつぶします。

さらに麺棒で上からつぶしました。

麺棒で押してみたり

そういえば、マッシャーがありました!これを最初から使えばよかったですね。

マッシャーもっと早くだしてくださいよ。。。
塩と糀を合わせる
塩と糀を合わせ、混ぜていきますが、この作業をする前には、雑菌が入ってしまったら大変なので、よーく手をあらってください。
アルコールの登場ですね。

それと、大豆の温度が60度以上のまま混ぜてしまうと、糀が死んでしまうので、これ以下の温度で混ぜるようにします。

我々は、つぶし方を吟味していたら、あっという間に温度が下がってしまいましたね。
糀をつぶさないようにしてしっかり混ぜます。

かたすぎたら、煮汁を少し加えてもいいですね

小指でさしてみて、すっと入る固さならOKです。

容器に入れる
ここでも、アルコールの登場。

入れる容器を洗い、中をアルコール消毒しておきます。
我が家では、ホーロー缶を容器にしてみました。

軽く塩をまいておきます。

ここでポイントです。小さなお団子を作ります。

お団子を容器に入れていきます。

お団子をつぶしながら入れていくことで、空気を抜いていきます。

つぶすの楽しいですね。

それを繰り返します。今回は仕込む量が少なかったので2回で終わりました。

表面を綺麗に平らにします。

綺麗すぎる!几帳面!
塩を1〜2つまみ、表面に振り入れたら、容器の内側をアルコールでふいて、きれいにします。
みそが少しついていたりするので、取り去っておきます。縁もきれいに拭きましょう。

ラップで表面をおおっておきます。
空気を入れないように、表面にぴっちりと貼ります。

難しいけど、なんとかできました。

その上から、重石をします。が、石ではなく、1kgの塩をビニール袋に入れて、上から乗せます。

全体に均等に力がかかるので、いい感じです。

湿気対策にキッチンペーパーを上からかぶせ、ホーロー容器にフタをします。

冷暗所に置いて、仕込み完成!

10月頃が食べごろになりそうです。熟成具合が楽しみです!
約6ヶ月後が経過。。。
半年後の味噌の様子です。

カビのように見えるのは酵母らしいです。カビかわからなくて取り除いてしまいました。

いい色に変化しているのがわかりますね。

塩は完全に重石の形になりました。

醤油がにじみ出ています。

自家製味噌の完成!
10ヶ月後!こんな感じの味噌が出来上がりました。すごい!

自家製味噌の為に「宮島細工のバターナイフ」を用意しました!

おっしゃれぇ〜
作ってみての感想
味噌作りは、2日間にわたっての作業になりました。大豆を水に18時間以上つけておくからです。
それでも、ラーメン作りに比べたら簡単なもので、見ていただいたように、少し気合いを入れれば、誰でもすぐにできるのが味噌作りです。
2月に作って、8ヶ月後の10月頃に若味噌ができあがります。
発酵する期間が短ければ大豆の色に近く、長いほど赤黒くなっていきます。
約8カ月~1年あたりまで、味の違う味噌がつくれるみたいです。
味噌作りは、作るだけでおわりではなく、待っている数カ月後が楽しみになるという素敵な食材です。
これを使った自家製お味噌汁もとても美味しいです!
自分の作る調味料が増えていくのはとても楽しいです。
[amazonjs asin=”B006AND5GW” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”味噌手作りセット 4kg用 樽付き”]