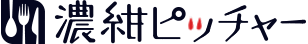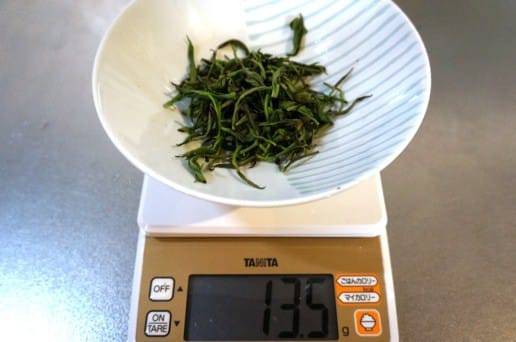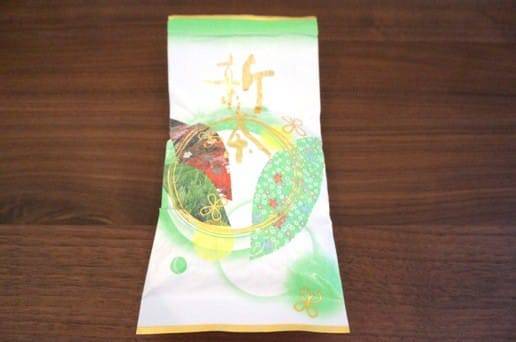浅草のうなぎ 色川
浅草の鰻と言えば!「色川」と答える方は多いのではないでしょうか。
何せ、文久元年(1861年)創業の老舗店。
こちらは、たっぷりサイズです。

最初に感想を伝えておきます
- 今まで食べていたうなぎと味が違う。
- 箸を入れると簡単にきれるやわらかさ。
- 炭の香りがいい。
- 山椒が香り高い。
価格が安いうなぎになると、いわゆる皮がゴムのように感じる事もありますが、これは全然違います。
「あぁ、これがうまいうなぎってやつなんだな。たしかにうまい!」
色川の店を出たあと、道を歩きながらそう言葉にしていたのを思い出します。
うなぎを食す
こちらがふつうサイズのうなぎ。お吸い物付です。


カウンターの山椒をかけて頂きます。

程よく焼き目がついた鰻は、ふっくらでタレがからみ、とても美味しいです!

色川の行列
そんな色川には、有名かつ美味しいお店として、多くの方が連日訪れます。
開店前から列ができるのは当たり前。

色川の外観です。

店内はこのようにこぢんまりとしており、カウンター4席と、テーブル(4人×2席)があります。

カウンターの上は山椒のみ。

棚の中もきれいに整頓されています。
こういう細かいところにも意識が届いているお店は素敵です。

職人さんのうちわです。歴史を感じます。

焼きの様子
たまたまカウンター席に座れたので、職人さんの焼いている様子を見ることができました。
丁寧に焼いているその姿は真剣そのもの。

メニュー
メニューはシンプルで、こんな感じです。
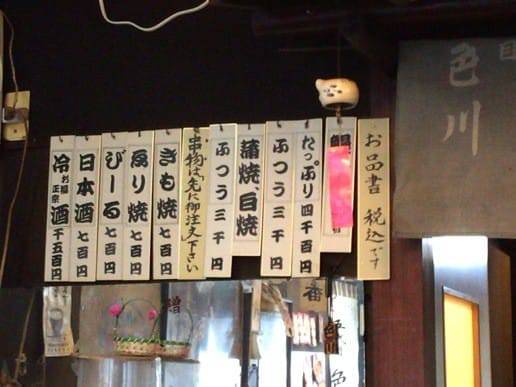
おわりに
11時30分から開店ですが、10時50分にはもうお客さんが前に並んでおりました。
早く並べば最初に入店できて、早く食べることができます。
14:00には終わると書いてありますが、売り切れ次第閉店となります。
浅草に行った際は、早めに並んで待つことをおすすめします。